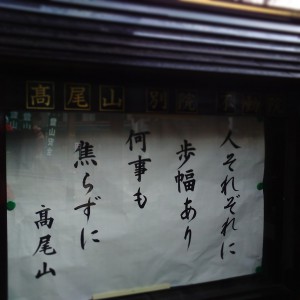牧師になって間もない頃、右も左も分からず不安でいっぱいだった私を、いつも笑顔で励ましてくださった方がいました。時々お訪ねしてお話しをしたり、一緒にお祈りをさせていただいていました。その方がことあるごとに私にかけてくださった言葉が今も心に思い出されます。
「私はもう外に出て行って教会の働きをすることは出来ないけど、その分あなたの働きのために毎日ここでお祈りしているからね。」
当時90歳だった彼女は、若い頃と同じように教会の働きをすることは出来なくても、自宅で牧師や教会の皆さんのことを一人一人名前を挙げて祈ることが、神様から今の自分に与えられた働きだと確信し、祈りによってたくさんの人たちを支えておられたのでした。
壁に突き当たり、途方に暮れるような時、この方の「あなたのためにお祈りしているからね」という言葉と、ささげられた祈りにどれだけ支えられたか分かりません。彼女はしばらく前に眠りに着かれましたが、今も私は彼女の祈りに支えられているのを感じます。祈りは弱った人を支え、その人がなすべき働きを成し遂げるために必要な力を与えるのです。
「しかし、わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」
(新約聖書 ルカによる福音書22:32 新共同訳)
 イエス様も弟子たちのため、そして私たちのために祈って下さいました。自分のために祈ってくれる人がいることを思うとき、自分も誰かのために祈り続ける信仰者でありたいという気持ちにさせられます。私たちが祈りによって誰かを支え、励ましあたためることが出来るというのは神様から与えられた祝福ではないでしょうか。
イエス様も弟子たちのため、そして私たちのために祈って下さいました。自分のために祈ってくれる人がいることを思うとき、自分も誰かのために祈り続ける信仰者でありたいという気持ちにさせられます。私たちが祈りによって誰かを支え、励ましあたためることが出来るというのは神様から与えられた祝福ではないでしょうか。
セブンスデー・アドベンチスト甲府キリスト教会 牧師 伊藤 滋
※写真は、厳しい寒さの中でこそ大活躍。憧れの薪ストーブです。